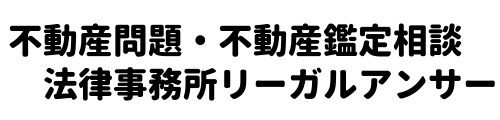1.よくある借地トラブル
東京都内や首都圏には数多くの借地があります。借地権も権利としての価値を有しており、東京都内の土地の価格は高いですから、同じように借地の価格も高額なものになり、借地とはいってもその所在地や面積によっては、極めて高額なものになることがあります。
そして、借地は、契約期間が50年以上のもの、中には戦前から契約しているものもあります。このような長期間にわたって借地権を有している借地人(賃借人)は、次第に借地権が自分の土地のような感覚になってしまうことがありますが、あくまで借りている土地に変わりがありません。
ですので、借地を第三者に譲渡する場合、借地上の建物を建て替える場合など、借地を処分するためには、地主(賃貸人)の承諾が必要になります。無断で第三者に譲渡したり建替えを行ってしますと借地契約の解除事由となってしまいます。
そして、賃貸人がこれらの変更を承諾してくれない場合には、裁判所に承諾に代わる許可を求めることになります。この手続きのことを「借地非訟手続」といいます。
賃貸人がこれらの変更の承諾してくれない場合に、無断で変更してしまうと契約違反になってしまい、借地権自体を失うことになってしまう場合もありますので、注意が必要です(借地非訟手続中も無断で変更することはできません)。
2.借地を巡る法律関係は複雑
借地を巡る法律関係は、当事者間で締結された契約だけでなく、借地借家法や旧借地法によって規律されています(戦前からの借地契約などでは契約書が存在しないケースもありますが、このような場合でも旧借地法が適用されます)。
借地借家法や旧借地法の規定の大半は契約によっても変更できない、法律に反する合意が無効になる強行規定とされており、借地を巡る法律関係を検討するに当たっては借地借家法や旧借地法の理解が必要不可欠となります。
また、借地借家法が制定された現在においても、借地借家法が制定される前(平成4年)に借地契約が締結されている場合には今日でも旧借地法が適用されるという点にも注意が必要です(借地借家法附則4条)。
このように借地を巡る法律関係は複雑ですので地主(賃貸人)との交渉及び借地非訟手続を行うのであれば、法律違反にならないように、また、交渉を円滑に進めるために弁護士に依頼した方が良いです。
借地非訟手続きに要する期間は、譲渡や建替えの承諾料だけが争点となっている事案でも1年程度はかかりますし、承諾料の他に(借地の利用を巡る)事実関係などに争いがある事案では2年程度の期間を要します。
3.不動産鑑定の知識が必要不可欠
借地を巡るトラブルは、地主(賃貸人)に対して承諾料を支払うにしても、更新料を支払うにしても、地代の増減額を争うにしても借地や地代の金銭的な評価が問題となります。
第三者への譲渡承諾についてみてみると東京地方裁判所で実施される借地非訟手続きでは、承諾料の水準が公表されていますが、この承諾料算定の基準となる借地権の価格については何ら基準が示されていません(借地権価格は土地ごとに異なるので基準を示すことが難しいのです)。借地権価格を決めるのは「不動産鑑定」ですから、不動産鑑定の十分な知識なしに借地非訟手続を行うことはできません。
借地非訟手続きの中で、最終的には裁判所が選任した不動産鑑定士による鑑定(裁判鑑定)によって承諾料などの価格が決定されるとしても、裁判鑑定がなされる前に十分な立証活動を行うことが極めて重要です。
「どうせ裁判鑑定で決まるのだから当事者に訴訟活動は意味がない」という意見もありますが、裁判所から依頼されて裁判鑑定を行う不動産鑑定士は必ず当事者が提出した鑑定評価書を確認しますから、その鑑定評価書に矛盾がなければそれに反する判断を行うことは極めて難しくなります。
なお、不動産の価格を決める指標としては、相続税路線価か固定資産税路線価などの基準が知られていますが、裁判手続きでは、これらの路線価ではなく時価評価を行いますので、これらの路線価はあくまで参考にしかなりませんし、不動産業者が作成した査定書などは考慮にも値しません。
4.弁護士費用
| 着 手 金 | 35万円~ |
|---|---|
| 報 酬 金 | 取得した借地権価格(ないしは介入権行使によって得た対価)を基準に算定 |
※上記はあくまで目安です。実際にご依頼いただく際は、契約前に具体的なお見積りをさせていただきます。