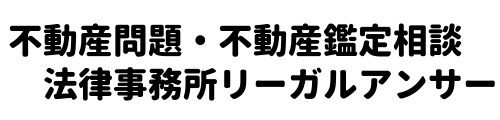賃料増減額請求を左右する「直近合意時点」とは?
賃貸物件のオーナーやテナントにとって、「賃料の増額や減額の交渉」は避けて通れないテーマです。特に、借地借家法32条1項に基づく賃料増減額請求では、「直近合意時点」という考え方が非常に重要なカギを握ります。
しかし、この「直近合意時点」とは一体何を指すのでしょうか? 実は、このポイントを誤解したまま交渉やトラブルに巻き込まれるケースが後を絶ちません。この記事では、トラブルを避けるために押さえておきたい重要ポイントを、専門家の視点からわかりやすく解説します。
1 そもそも「直近合意時点」とは?
「直近合意時点」とは、オーナーとテナントが最後に賃料について正式に合意した時点を指します。この合意は、更新契約や覚書、口頭合意など形態を問わず成立する可能性がありますが、後々のトラブルを防ぐためには合意内容をきちんと記録に残しておくことが重要です。
この「直近合意時点」が、将来の賃料増減額請求のスタートラインになるため、何を基準に賃料を見直すかという点で、非常に重要な役割を果たすのです。
2 なぜ「直近合意時点」が重要なのか?
賃料の増減額請求が認められるかどうかは、「直近合意時点」と現在(価格時点)の状況を比較して、その間にどれほど状況が変わったか(事情変更があるか)がポイントになります。
例えば、
・合意当時と比べて、周辺の賃料相場が大きく変動している
・建物が老朽化し、大規模リノベーションを行った
・コロナ禍や経済情勢に大きな影響が出た
このように、「直近合意時点」と現在(価格時点)の状況を客観的に比較することで、適正な賃料を判断していくのです。
3 ここが落とし穴!「直近合意時点」の認識ズレがトラブルに
実は、「最後に賃料を合意したのはいつか?」という認識が、オーナーとテナントで大きくズレていることも珍しくありません。
例えば、オーナーは「10年前の更新契約」を直近合意だと考えている一方で、テナント側は「5年前の賃料交渉で口頭合意した内容」を直近合意だと認識している——こうしたズレは、賃料交渉を混乱させる大きな要因になります。
このような認識のズレを放置したまま交渉や請求手続きを進めてしまうと、話し合いがまとまりませんし、裁判もできなくなってしまう可能性があります。
4 直近合意時点の決定方法とは?
「直近合意時点」は、契約書や覚書があればすぐに確定できると思われがちですが、実際にはそう簡単ではありません。交渉過程で口頭合意した内容が記録に残っていなかったり、双方の認識が微妙に食い違っていたり、合意自体の効力や有効性に疑問が生じるケースも少なくないからです。
こうした事態を防ぐためには、①過去の契約書や覚書の精査 ②交渉履歴やメール・LINEなどの証拠整理 ③合意の実行性の確認 ④複数の合意が存在する場合の整理などが必要になります。特に、オーナー側もテナント側も「自分に有利な合意時点」を主張しがちですが、裁判所がどのように評価するかは、法律の専門知識と過去の判例に基づく判断が不可欠です。
5 まとめ 〜弁護士×不動産鑑定士の強みを最大限活用〜
賃料増減額請求において、「直近合意時点」の認定が交渉結果や裁判結果に与える影響は非常に大きなものです。
大丈夫と思っていても、過去の交渉経緯や契約内容を改めて確認すると、思わぬ見落としや認識違いが発覚することもあります。こうしたリスクを回避し、有利に交渉を進めるためには、不動産トラブルに強い弁護士への早期相談が不可欠です。
特に、法律事務所リーガルアンサーの代表弁護士は、不動産鑑定士と弁護士のダブルライセンスを持つ専門家です。不動産鑑定士として、物件の特性や周辺相場、経済動向を踏まえた適正賃料を算定するだけでなく、その結果を法的根拠に基づき、裁判所にも伝わる形で主張・立証できる点が最大の強みです。
さらに、交渉段階から裁判まで一貫して対応できるため、交渉での譲れないラインや証拠収集のポイントを踏まえた戦略的な対応が可能になります。
不動産の適正価値を正しく把握し、法律的な裏付けをもって有利に交渉を進めたい方は、ぜひ法律事務所リーガルアンサーにご相談ください。