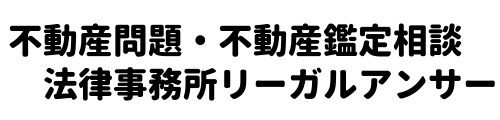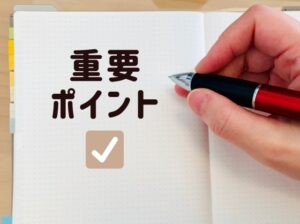賃料増減額請求の流れについて
当事務所には、不動産関連のご相談を多数いただきますが、その中でも、代表弁護士は不動産鑑定士資格を有する弁護士であることから「建物の賃料が周辺相場に比べて安いので、家賃を上げたい」とお問い合わせを頂くことが特に多いです。
借地借家法では、建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求できると規定しております(借地借家法32条1項本文)。
それでは賃料増減額請求をしようと考えた場合、どのような対応が必要になるのでしょうか?今回は、具体的な流れについてご紹介いたします。
1 賃料増減額請求
まずは、借地借家法32条1項に基づいて賃料増減額請求を行います。賃料増減額の効果は賃料増減額請求時点に遡って効力を生じるため、賃料増減額請求は書面で行い、証拠として保存しておく必要があります。
2 裁判前・裁判外の交渉(任意交渉)
賃料増減額請求後、相手方と裁判前・裁判外での交渉(いわゆる「任意交渉」)を行います。ただし、任意交渉で、相手方がこちらの提案額を受け入れることは少なく、賃料の変更自体を拒否されることもあります。
相手方がこちらの提案を受け入れない、交渉のテーブルにも付かない場合には、調停申立に移行します。
3 民事調停申立
賃料増減額請求は、法律上、訴訟を提起する前に民事調停を申し立てる必要がある「調停前置主義」が採用されており、調停を経ることなく訴訟を提起することはできません。そのため、任意交渉が不調に終わった場合には、まずは裁判所に調停を申し立てることになります。
調停は、裁判所へ申立後に初回期日が指定され、多くの場合、初回期日は申立てから1か月半程度経過した日が指定されます。
初回期日では、裁判所を交えて相手方と協議を行う調停手続が開催されます。
期日で双方の主張を述べるほか、期日までに双方の主張を書面で回答することが一般的で、かつ、複数回期日が開催されます。調停での双方の主張に隔たりが大きい場合には、調停での解決は困難ということになり、訴訟に移行することになります。
4 訴訟
訴訟では、専ら当事者が提出した不動産鑑定評価書などの証拠に基づいて主張反論を行います。そして、双方の主張が出尽くした段階で、裁判所が選任した不動産鑑定士による裁判鑑定を実施することになります。
裁判鑑定の結果が示されると、裁判所の判決における判断も、ほぼ裁判鑑定の結果に拘束されます(明らかな間違い等がない限りは裁判鑑定の結論が採用されます)。そのため、裁判鑑定までに提出した不動産鑑定評価書の正当性を十分に主張する必要があります。
以上が、賃料増減額請求をした際の流れとなります。
賃料増減額請求は、貸主・借主共に認められている権利となりますが、相手方と話し合いで解決できない場合には、上記の通り法的手段が必要となってきます。具体的な事案のご相談は、不動産問題を得意とするリーガルアンサーまで、お気軽にお問い合わせください。