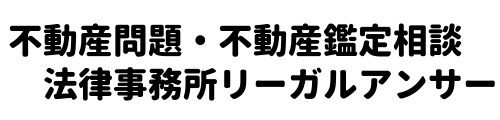不動産の無償使用(使用貸借)と相続
1 使用貸借とはどのような権利か
父親名義の土地の上に相続人である子名義の建物が建てられており、父親の生前、建物所有者である子から土地所有者である父に対して何らの支払いもないまま子が無償で土地を使用しているという場合、子が無償で土地を使用していたという事実は相続において法律上どのように評価されるでしょうか。
上記のように、子が、親が所有している土地を無償で使用していること、すなわち、無償で他人の物を使用する法律関係のことを「使用貸借」といいます。
民法上、使用貸借とは、無償で使用及び収益をした後に返還することを約束して相手方から不動産などの物の貸借を受ける契約をいいます(民法593条)。
使用貸借と同じように物を使用及び収益した後に返還することを約するものとして賃貸借があります。
賃貸借と使用貸借の違いは、賃貸借が使用・収益の対価を支払うべきものであるのに対し、使用貸借は無償で使用・収益できる点が異なります。使用貸借は対価性を有しない契約ですので、賃貸借と比較すると借主の権限も弱いものに留まっております。
使用貸借は、無償で使用・収益を行うものですので、家族関係など契約以外の一定の関係が存在する場合に設定されることが多い契約です。
2 相続税における使用貸借の位置づけ
相続税の計算においては、使用貸借は、当該財産に使用貸借が設定されていたとしても、当該財産の財産評価に影響を与えないとされています(国税庁HPタックスアンサー「宅地の評価単位―使用貸借」、財産評価基本通達7-2)。
これは、使用貸借が、借主が死亡した場合には権利が消滅するとされていることなど(民法599条)、賃貸借と比較すると権利としての保護が弱いため、財産として評価する必要がないという判断に基づいていると考えられています。
3 遺産分割における使用貸借
(1)遺産分割における使用貸借
相続税の計算ではなく、遺産分割の場面では、使用貸借といっても、財産として評価すべき場合、つまり、相続に当たって使用借権を考慮すべき場合があるとされています。使用貸借であっても、一律に権利として保護されていないわけではなく、ケースによっては、相当程度権利として保護される場合があるからです。
この問題は、①相続財産の算定の際に使用借権が設定されている不動産をどのように評価するかという問題(使用借権と不動産鑑定評価)と、②使用借権が設定されている期間、借主は無償で土地を使用しており、その使用の対価である賃料の支払いを免れたことが特別受益に該当するのではないかという問題(使用借権と特別受益)の2つの場面で問題になります。
(2)土地の使用貸借について
土地使用借権の不動産鑑定評価について
①の使用借権が設定されている土地の評価については、使用借権が設定されている土地は、使用借権相当額を減価して土地の評価を行うことになっております。これは、使用貸借が設定されている土地については売却が困難(建物は第三者の所有であるため土地所有者ないしはその譲受人は建物を使用することができません)であることが理由とされているようです。
土地の使用借権の評価については、明確な基準はありませんが、一般的には、地上建物が非堅固建物(木造・軽量鉄骨など)の場合には使用借権の価値は更地価格の1割程度と評価され、堅固建物の場合には使用借権の価値は更地価格の2割程度と評価されることが多いようです。
堅固か非堅固かによって価値が異なる理由は、権利として保護の程度が強いか弱いか異なるためであると言われていますが、非堅固か堅固かで取り壊しの費用や困難性に相違はあっても権利として保護の程度に違いはないと思われますのでその理由の論拠については疑問があるところです。
むしろどのような使用借権が設定されているか分析した上で(民法597条参照)、使用借権としてどの程度保護されているか判断し、その保護の程度によって価値を決めるべきだと考えます。
土地使用借権と特別受益について
②の特別受益に該当するという点については、使用借権が設定されている期間、土地を無償で使用できたという利益については、土地の使用貸借で得られる利益は賃貸借と比較すると弱い(保護の程度が低い)ことなどを理由に、遺産分割に当たっては特別受益として評価しないことが多いです。
(3)建物の使用貸借について
建物使用借権の不動産鑑定評価について
建物の使用貸借については、土地の使用貸借契約と異なり、建物の使用借権を有していても財産的価値はないとされています。これは、土地の使用借権ほど明渡しが困難ではないことなどが理由とされているようですが、土地の使用貸借と比較したときに、権利として保護されているか否かは土地か建物で相違はないですので、土地と建物で結論を異にする明確な理由はないといえます。
このような結論に至る背景には、次のような事情があるように思われます。
別居して生活していた子が、親の介護のために、親と同居し、親の介護を行うようなケースが増加しています。このようなケースで、子が親と同居した事実のみをとらえて、子が使用貸借によって賃料(家賃)の支払いを免れていると評価することが適切ではない場合が多いため、建物の使用借権については財産的評価を行われないと考えられます。
建物使用借権と特別受益について
使用借権が設定されている期間、建物を無償で使用したことによる利益をどのように評価するかについては、建物を無償で使用したことによる利益を財産的に評価しないと考えられています(特別受益として考慮しない)。親が戸建住宅の一室を子に使用させていた場合などは、概ねこの結論に異論はないところですが、親が一棟マンションを所有し、その一室を子どもに無償で使用させていた場合などには、無償で使用していたことによって得た利益をきちんと評価することが適切な場合もあると考えます。
以上
参考条文
民法597条(借用物の返還の時期)
1 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
3 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。